星のきれいな島で【5】青春“図書館”編 (ボクとボクらの話)

11月8日を「ふきのとうの日」に決めた、みっちゃんとわたし。
それがどうした、と言われればそれだけの話だが、「わたしと彼」のその後のことについて書いてみたい。
待ち合わせ場所
あの日以来、わたしたちは、ほぼ毎日のように会って話をした。
携帯電話はなく、固定電話も、アパートの大家さんの所にしかなかった時代。
学生同士が連絡を取り合うのは、直接会うことだった。
わたしたちの待ち合わせ場所は、学校の図書館で、昼の12時から午後1時までの間だった。
彼の友だちが立ち寄りそうもないという理由からこの場所が選ばれた。
また、時間は昼食の時間帯ということで、図書館から学生がいなくなる時を狙ったものだった。
わたしたちは、別に悪いことをしているわけではないのだが、2人とも照れ屋で、恥ずかしがり屋で、人見知りで・・・、数え上げたらきりがないほど、人付き合いに向いていない性格だったので、こういう待ち合わせ方法になった。
街に行く前の儀式
わたしたちは、図書館で会い、午後の予定を決め、彼のバイクで彼のアパートへ行った。
彼は家に荷物を置くと、すぐに外で待っているわたしの所へ来て、「”ねえねえ”からね」と、近くの食堂の人のものまねをした。
「“ねえねえ”からね」は、「“ねえねえ”(お姉さん、女性のこと)の方を先にしますね」という意味。
その食堂では、食べるのが遅いわたしのことを気づかって、わたしが注文した料理を先に作って持ってきてくれた。
「“ねえねえ”からね」、この彼の言葉が、悔しいやら、うれしいやら、恥ずかしいやら・・・。
わたしは、彼のものまねが終わると、すぐに自分の肩を彼の体にぶつけた。
こんなささいなやり取りが、いつのまにか、2人が街へ行く前の儀式になった。
「女の子を乗せてバイクで走ってると、“からまれる”のがいやだから」という彼の意見を尊重し、わたしたちはバスで街へ向かった。
街では、映画を見たり、お互いの買い物に付き合ったり、ファストフード店に行ったりした。
わたしたちは楽しいことがあると、お互いの肩をぶつけ合いながら街を歩いた。
その様子は、わたしたちのことを知らない人から見ると、仲のいいきょうだいがじゃれあって歩いているように見えたことだろう。
昨日の彼のこと
12月も半ばにさしかかった頃、みっちゃんと学校の近くの喫茶店で久しぶりに話し込んだ。
前の日に開かれた「留学生のお別れ会」に参加したみっちゃんは、彼や彼の友人もその会に参加していたことや、会が終わった後、珍しく怒った彼が、彼の後輩と言い合いになったことも教えてくれた。
みっちゃんが心配していたのは、そのとき、彼がわたしのことを「彼女じゃない」と言い、わたしたちは「付き合っていない」と言ったことだった。
「ねえ、あなたたち、どうなってんの?」
みっちゃんがわたしに聞いてきた。
わたしは、あの日から、彼とほとんど毎日会っていることや、街へ遊びに出かけていることを話した。
そして、「彼と会っているとホッとする」という自分の気持ちを素直に話した。
「それはそれは、よろしゅうございますねえ。では、昨日の彼は何なの?」
わたしが黙っていると、みっちゃんは「聞いてきてあげようか」と言った。
わたしは、この前のことで懲りているので、「後で、会って聞いてみる」と言い、一緒について行ってあげようかというみっちゃんの親切を「ごめん、自分でちゃんとするから」と言って断り、みっちゃんと別れた。
時刻は、もう夕方近くになっていた。
「ごめんね」「何が?」
わたしは、彼のアパートに行ってみた。
するとバイクがない。
わたしは、バスで学校へ引き返し、閉館時間(午後7時)前の学校の図書館に行ってみた。
すると、入り口にバイクがあり、談話室に彼がいた。
「遅いから、1冊読んじゃったよ」というのが、わたしを見かけたときの彼の第一声だった。
わたしが「ごめんね」と言うと、彼は「何が?」と言って、スポーツ新聞をすみずみまで読んだことや、わたしがすすめた本を読み終えた後の感想を言った。
閉館時間が近づいていることを知らせる音楽が鳴り始め、わたしたちは、裏口から出てバイクの置いてある場所へ向かった。
並んで歩きながら、わたしは、思い切って聞いてみた。
「ねえ、わたしたちって、付き合っていないの?」
彼は、前を見ながら、「あいつ(彼の友人)から聞いたの?」と尋ねた。
「ううん。みっちゃんから」と言うと、彼は、「明日、昼、図書館」と言いながら、バイクのエンジンをかけた。
いつもよりくっついて
わたしは、ステップに足をかけて、バイクの後ろのシートに乗った。
わたしが彼のジーンズのベルトの所に手を回すと、彼はいつものようにバイクをスタートさせた。
彼の家を過ぎた後、「近くのバス停まで送って行く」と彼が言った。
わたしは、自分のヘルメットを彼のヘルメットにコツンとぶつけて、「わかった」と合図をした。
そのとき、アメリカンフットボールのユニフォームを模した彼のトレーナーから、そのデザインとは程遠い、ミルクのような、石鹸のような甘い香りがした。
わたしは、少し横を向き、その香りにもたれかかるように、いつもより彼にくっついた。
わたしの家の近くのバス停に着き、わたしはバイクからおりた。
彼はバイクのエンジンをかけたまま、わたしからヘルメットを受け取り、左腕に腕輪のようにヘルメットを引っ掛けた。
そして、「明日、昼、図書館」と、さっきと同じことを言って、彼の家の方に向かって帰って行った。
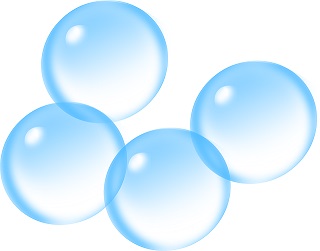
※ この物語は、フィクションです。
※ 続きは、下記リンクをご覧ください。



